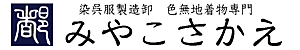「菊は秋に咲くから、秋以外着てはいけない」
当店のお客様が言われたそうです。
「秋なので菊柄にしました」は、もちろん問題ないです。

「秋以外着てはいけない」は、、、。
しかもわざわざ他人様に、、、。(親切心からでしょうが、、)
あのー、菊文様は少し違うんです、と言いたい。
他にも有名なものですと松・竹・梅・蘭・桜・菊。
季節を超越した、最強のとても凄い別格の植物文様達がある、と言いたい。
で今回は、菊のお話。
知識を持っていると人に言われても安心ですし。何より面白いです。
色々調べますと菊は、特別な植物です。色々な時代の背景が混ざり合って今の菊文様となっております。
《1香りが良く美しい》
菊はもともと中国原産の植物、中国ではすでに周の時代(約二千三百年前)に栽培されていたらしいです。
シンプルに香りが良く、姿が美しいのが愛でられるきっかけでしょう。

先秦には、菊花観賞が『礼記』にしるされています。
その後、何度か菊の鑑賞ブームがありますが大きく発展したのは宋の時代。現代見られる菊の原型のほとんどがこの時代に作られたそうです。
日本では最初、「貴族の花」でありましたが江戸時代に庶民が愛でるようになります。
植物としての菊は、秋の花で、和歌などにも歌われることとなります。
《2、呪術的要素》
先秦の頃、神仙思想と結びつくようです。神仙思想は簡単にいうと仙人・神人になる事目指す。
で、何が目的かというと、、、不老長生。
それで菊は延命長寿の霊草 として珍重されます。
不老不死の仙薬の仙花であるわけです。
「菊にひたされた水は生命の水、不老長生の水」
秦の始皇帝が不老不死を願って仙薬を血眼になって探していたのもこの頃。
「白菊と蓮花、ニワウルシの花汁を丹(硫化水銀)に和して蒸して服すること1年を経れば齢500歳」といわれる
最初、植物だけの調合だったのが鉱物も混ぜだします。
この丹は、血の色みたいに赤いから効くはずという、現代人には恐ろしい理由だったそうでほとんど呪術なのですが、当時は大真面目で最新医療。
始皇帝や唐の皇帝が早死にしたのも、仙薬のつもりで飲んだ水銀の中毒だったとされています。
菊は、ビタミンEが豊富ですので、老化対策位の効能はありますから、菊だけ飲んでいたなら長生きして歴史が変わっていたかもしれません。
中国最古の薬物書『神農本草経』に上薬として登場します。
「味は苦平。風による頭眩や腫痛、目が脱けるように涙出するもの、死肌、悪風、湿痺を治し、久服すれば血気を利し、身を軽くし、老に耐え、年を延す。一名節華」と記される。
何か難しいですが、効きそうです。
「宮廷人がはじかみを食し、菊酒を飲んで長寿を願う」
漢代には、重陽の節句の原型のような振る舞いが行われていたようです。この辺りが延命長寿のいわれの流れ。
今と違うのは当時の人はマジでやっていたということ。
日本では、貴族たちが当時の中国に憧れて、模倣をする訳です。
当時の優秀なエリート達が真剣に厳かに取り組んでいたみたいです。こちらも現代人の「長生きできると良いね」位の軽い雅な感じではなかったようです。貴族怖い。
《3、百花の王》
菊は、本草経では別名「日精」と呼ばれ、菊の花弁が放射状の形状を日輪に見立てる考えが表れています。

古代メソポタミアの太陽神のシンボルが同じような菊文様ですので、もしかしたら、この辺りの思想が伝播していたのかもしれませんね。
太陽の精気を含んだ花、百花の王。別格の花とされているわけです。
ちなみに天皇家の家紋が菊なのは、後鳥羽上皇の菊好きが由来なのですが、太陽神であります天照大御神の子孫が日精の家紋というのも面白いです。
それで日本では、奈良時代、秋草のひとつにすぎなかったようなのですが平安時代初期には、上記のような中国の観念、習俗が定着して、和歌に歌ったり重陽の節会が始まったりします。最終的には最も高貴なものという観念まで昇りつめることになります。
《4、倫理的シンボル》
11世紀の宋の時代、菊の鑑賞ブームが起こり、色々な品種が作られます。
また、同時に延命長寿の仙薬の毒性が有害であるとされます過程で、呪術的なシンボルから菊は四君子の一つ、倫理的なシンボルとなっていきます。
「菊は万物の花が枯れ落ちる季節に、一人その美しい花を咲かす。堅固な精神を持つ証」
「高雅な香りは徳の高い印」
とされます。
《5、純粋に美の象徴》
江戸時代は、菊の鑑賞が盛んな時代。
様々な新しい品種が作り出され、各地で菊の会が開かれその美しさを競い合うようになります。
菊の栽培の庶民への普及につれて、上記でのべた ,呪術性や倫理性、季節性などから解放された美しいデザインとしての菊柄が誕生します。
実際の菊を品種改良して、どんどん綺麗で洗練された菊が生まれますから、それに従って、衣装や調度品に美しい菊の文様が生み出される事になります。
それまでの秋草の中の一つとして描かれたり、長寿のシンボルとして水とセットで描かれる必要がなくなります。衣装の文様にも菊単体で美の象徴としてデザインされ、盛んに用いられるようになります。
調べだすときりがないのですが、色々な時代の思想や背景がてんこ盛りの文様でして、様々な意味を内包している文様であります。
せっかくの美しい文様ですから、着れない理由をわざわざ探すのではなく、着れる理由を探して沢山着てください。
色無地 みやこさかえ